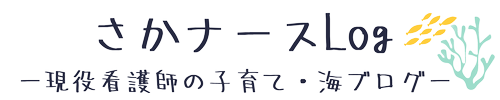愛育病院(田町)で出産を考えている方!

「外来はどうやって受診するの?」
「NST・助産師外来って何するの?」
「外来の様子を知りたい!」
と気になることは多々あると思います。
私は愛育病院で無痛分娩し、外来の時から満足する受診ができました。
事前に外来について知っておくことは安心に繋がります!
看護師や医師とコミュニケーションを取ることが出産の不安を減らすポイントです。
なので外来を最大限に活用できるよう、ここでは私の体験をお話しします!
「オープン・セミオープンシステム」を導入
一般的に妊婦健診は分娩する病院で受けます。
愛育病院の場合はそれとは別にこのシステムを外来で導入しています。
2つの違いはこちら↓
※詳しくは愛育病院のホームページを参照してください。
実はこれ東京都の委託事業として行なっていて、まだ山王病院や聖路加病院など大きな病院ではありません。
私はセミオープンシステムを利用していましたがとても便利でした!!
セミオープンのメリットとデメリットは以下の点です。
- 提携先の診療所が自宅や職場近くにあれば移動の負担が少ない
- クリニックの方が待ち時間が短い
- 妊婦健診や検査の費用が安い
- 提携先の数が多い
- ハイリスクの方は利用できない
- 妊婦健診の時と分娩する時に診る医師や看護師が異なる
- 妊婦健診の途中、トラブルが発生すれば愛育病院への通院に切り替わる
私は移動や待ち時間の負担が軽減されたことが特に良かったです。
外来
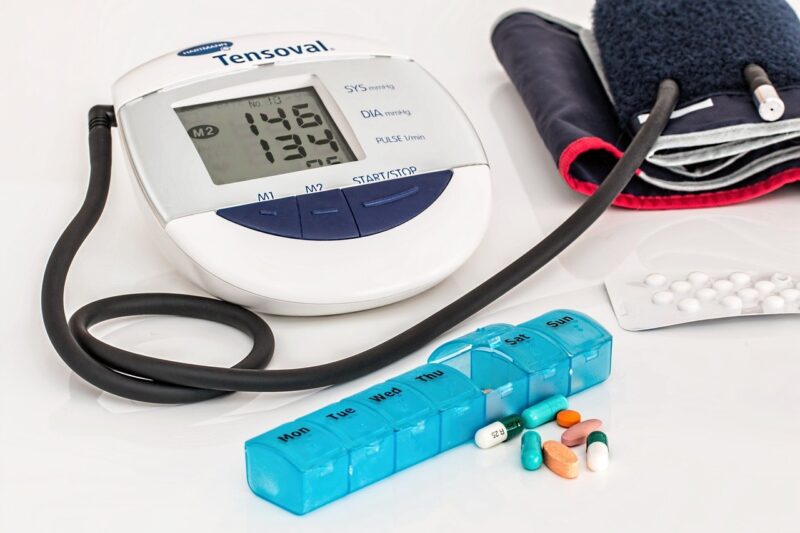
私は切迫早産になり予定より早めの33週から愛育病院に通院し始めました。
なので分娩まで計6回しか外来は受診していませんが、その中でも分かったことをお話しします!
受付
病院に着いたら、
- 2階の窓口で受付し、ページャー(診察の順番が来ると鳴る機械)を受け取る
- 初診時は提携先の紹介状など提出書類があったらここで提出する
ページャーを持ったまま一度駅まで散歩した際、「電波が届きません。近くまで戻ってください!」のようなメッセージと共に警報音が鳴り続けてヒヤヒヤしたので気をつけてください。笑
また、紹介状も最初の窓口で渡さないと中での連携がうまくいかず、私は無駄に待ちました。
検査・診察
受付が終わったら、
- 採尿(採血)のために別の窓口に行ってコップをもらい、トイレで提出
- 診察前にある体重計で体重を測ったら出力された記録用紙と母子手帳を持って診察室前で待機
平日の午前中に行くことが多かったですが、待ち時間は30−40分程度で思ったより待ちませんでした。
会計時間も含めると1時間弱で外来が終わる感じでした。
医師について
診察の先生は予約時に自分で選べます。
私は色んな先生に見てもらいたかったのであえて毎回違う先生にしました。
1回だけ男の先生でしたが、女の先生が多い印象でした。
どの先生も優しく、丁寧でさすが愛育病院だなという感想です!
ただ、精密超音波検査の先生はいかにも仕事できそうなこわーい雰囲気の女医さんで。
30分間、一言二言説明あっただけで後半はほぼ無言でした。笑
精密超音波検査っていうぐらいだから色々説明してくれるのかと思いきやちょっとこれは期待外れでした。
でも、最後に「はい、特に問題なかったですね〜経過良好です。」で終わったので相当何もなかったんだなと思って逆に安心しました。笑
NST
NSTは基本は36週・38週・40週以降に行います。
NSTの回数は医師から指示があった場合のみ毎回になることもあります。
私はウテメリン(お腹の張り止め)内服+自宅安静が37週まで続きましたが、そんなに緊急性がなかったのでNSTは基本の回数と一緒でした。
NSTの部屋は同伴者は入室できず、簡単にカーテンで仕切られているような部屋なので他の妊婦さんもよく見えます。
40分前後、お腹にセンサーをつけてリクライニングチェアに寝ながら携帯をいじったりぼーっとしたり、何してもいいです。
ただ体動がある時にボタンが押さないといけないので完全に寝ないようにした方がいいです!
助産師外来
ある時期になると経過が順調な妊婦さんは医師と助産師の健診を交互に利用できます。(例:今日の外来は医師の診察、次回の外来は助産師、その次の外来はまた医師、という意味です。)
- 医師の診察より安く済む
- 30分枠なのでゆっくり助産師さんとお話できる
- 内診はなし
- 超音波検査はあるが赤ちゃんの体重測定はなし
助産師さんからはバースプランの書き方、陣痛がきた時の対応についてお話しがあります。
私は希望で乳房マッサージの方法を教えてもらい、実際に母乳が出て感動しました。
また質問タイムの時は以下のことを聞いてみました。
解答:やらないよりはやった方がいい。でも初産婦はほぼ全員(会陰が)切れる。
その助産師さん曰く、初産婦は外国人の方は伸びやすいが日本人はほぼ切れるそうです。やらないよりはやった方がいいが、あまりデータに有意差はないそうです💡
解答:正直エビデンスがないので気にしなくていい。
その助産師さん曰く、食べたものが分子レベルで血液に流れるがそれが血液をドロドロにして詰まるということは医学的には考えずらいそうです。
ただ昔の助産師さんはそういう風に習っているのでそう指導する人が今でもいるみたいという話でした。
ちなみに私は産後乳腺炎になりました。
甘いものを気にせず食べ、珍しく牛ステーキを食べた翌日になったので「やっぱり食べ物か!?」と思いましたが助産院の助産師さんも愛育の助産師さんと同じ見解でした。乳腺炎の原因は「食べ過ぎや疲労で胃が荒れて体の血の回りが悪くなり、免疫力も低下するので乳腺炎になった」ということでした。
確かにその時期は夜泣きで寝不足&疲労が蓄積されてて口内炎もできていたし、母乳育児ですぐお腹が空くのでよく食べて胃に負担がいってました。なので免疫力と胃に負担をかけない食事が大事みたいですね!
質問は妊娠前、産後のこと、入院生活のことなど何でも聞けます。
事前に助産師さんに聞きたいことはメモをしておきましょう!
レストラン

愛育病院の最上階(9階)に小さなレストランがあります。職員さんも使う食堂です。
カツ重を頼みましたが味も美味しかったですしボリュームもあります!
お値段は1000円前後のものが多かったです。
出産準備クラス(麻酔分娩学級)

愛育病院には、
- マタニティクラス
- 両親学級
- パパママクラス
- ふたごの出産準備クラス
- 麻酔分娩学級
など数種類の出産準備クラスがあります。
内容はどれも豊富そうですが1個の受講料がお高めのお値段設定でした。
例えば私が気になってた「両親学級」は3日間で1コース16,500円でした。
ただ「マタニティクラス」は自分が気になるテーマ(「栄養のお話」など)だけを受けられるようになっています。
1テーマは1650円(1100円のものもあり)で受講でき、これはお得に感じました。
しかし残念ながら私の時はコロナ禍だったので全て中止でした。
それでも麻酔分娩学級は未受講だと無痛分娩が25万、受けていれば20万と5万の差ができちゃいます。
なので、この時は受講はできないけれど2000円払って資料と同意書をもらえました。
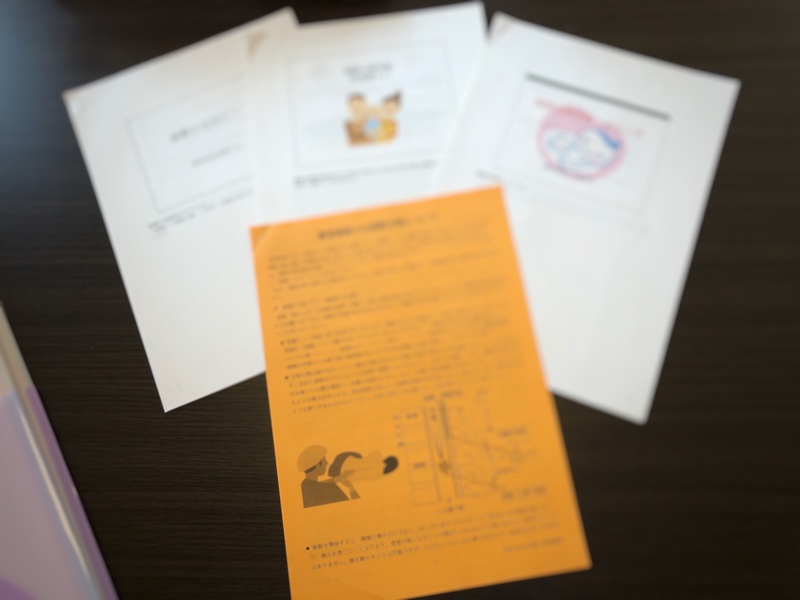
産婦人科医、麻酔科医、助産師とそれぞれの方が作ったパワーポイント資料と同意書(オレンジ色)がセットになってます。
内容はとても分かりやすく書いてあると思いますが、やはり麻酔が怖い人や麻酔の仕組みが分からない人にとっては紙だけじゃ伝わらないこともあるかなと思いました。
しかし安心してください!
その後、私が正産期に入った頃には麻酔分娩学級を含めた全ての出産準備クラスがオンライン受講できるようになってました!
なので今は対策がされているのでもっと気楽に受講できると思います。
またお値段もオンライン価格になっているものもあるのでぜひ確認してください。
講習の予約は診察室前などに掲示してあるQRコードを読み取るとできるシステムになってます。(2020年8月時点)
最後に
外来のイメージはつきました?
愛育病院の外来は医師や助産師、事務員の対応は良かったので、安心できる病院でした。
積極的に不安なことはスタッフさんに相談していきましょう。
安心なお産のためには外来をうまく活用していくのが大事です!
この記事が参考になれば幸いです♪
ベビーワゴンが気になる方に